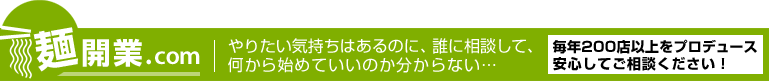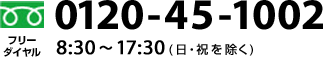いよいよ今年も残すところわずかになり、このフェイス・ブックは、元旦から1日も休んでいないので、343日間、連続で掲載していることになります。
休まない習慣が出来ると、不思議なもので、絶対に休めなくなるのです。
私が飲酒を止めたのも同じで、14年以上も止めていると、もう他人が美味しそうに飲んでいても平気で、飲もうとは思わなくなります。
良い習慣でも悪い習慣でも、継続するものです。
私には、まだ悪い習慣が残っているので、良い習慣を残し、悪い習慣を早く捨て去らねばと思っております。
そして、現在はドラッカー・マネッジメントの復習をフェイス・ブックに掲載していますが、ドラッカー・マネッジメントを改めて復習すると、たくさんの学びが得られます。
既に一通り学んでいるはずですが、まだ自分のモノになっていない部分、足りないが分かります。
自分の言葉で説明出来ないで、普段の行動になっていない部分は、まだ十分に身に付いていない部分です。
完全に身に付いていれば、大切な決定での判断がぶれることはなくなります。
従って、ドラッカー・マネッジメントも完全に身に付き、自分のものになり、自然と行動がそのようになり、習慣になるまで復習し続けなければいけないのです。
そして、私には毎月4日間、真剣勝負の経営講義があるので、経営講義で使えば使うほど、反復学習が出来、身に付く速度が加速します。
従って、経営講義は私にとって、たいへん素晴らしい学習の場になっています。
新しく学んだ概念を使い、経営講義でさまざまな方向から説明することにより、私にとっては素晴らしい反復学習になるのです。
今回、社内のスタッフに順番で経営講義に参加して貰っていますが、私の経営講義の難易度が最初頃とは比較にならない位高くなり、参加する生徒さんたちにとっては、たいへんだと思います。
普段このような勉強をやっているように見えない生徒さんでも、ガッツのある生徒さんは、繰り返し、私の経営講義に参加して理解しようと、たいへんな努力をしています。
そのような生徒さんを見れば、この人はこれだけガッツがあるので、開業しても絶対大丈夫だと信頼出来ます。
従って、私の経営講義は新規に麺専門店を開業する生徒さんにとっては、成功するかどうかを見極めるリトマス試験紙のような役目を果たしているようです。
いい加減な理解度で、開業する生徒さんは、開業後、店舗を訪ねてみると、経営講義で教えたこととぜんぜん異なることをやってしまって上手くいっていない場合が多いのです。
特に、小さい店の場合は席の取り方は非常に重要な事項です。
本日も、ドラッカーの名言の解説で、今日のテーマは「組織は目的ではなく手段」です。
21.組織は目的ではなく手段
組織が存在するのは組織自身のためではない。
自らの機能を果たすことによって、社会、コミュニティー、個人のニーズを満たすためである。
組織とは目的ではなく手段である。
(解説)往々にして、組織が出来ると組織の生存のためが大義名分になっているのですが、ドラッカーはそれに対して、組織が存在するのは組織自身のためではなく、社会、コミュニテイー、個人のニーズを満たすためであるとしています。
組織の本質については、さまざまな情報源に取り上げられていますが、参考になる事例として、「All About ビジネス学習 (執筆者:國貞 克則)」より、以下のように引用しました。
「組織の果たすべき3つの役割」
ドラッカーは社会全体を生命体として見ていました。
社会を構成する組織や個人が、その社会に貢献しているから社会は成り立っています。
ですから、社会の中の組織はどれも社会に貢献するために存在し、社会に対するそれぞれの役割を果たさなければなりません。
ドラッカーはすべての組織には3つの役割、「貢献」と「成果」、そして「人間の幸せ」があると言います。
ドラッカーの考え方は常に理路整然としていて、「ドラッカー経営学の基本思想」で説明したように、ドラッカーは社会全体を生命体として見ていました。
社会を構成する組織や個人が、社会に貢献しているからこの社会は成り立っていて、社会の中の組織はどれも社会に貢献するために存在します。
それぞれの組織は自らの仕事を通して具体的な成果を出し、社会に対するそれぞれの役割を果たさなければなりません。
つまり、組織の目的は組織の外にあり、組織の外に対する「貢献」と「成果」はドラッカー経営学の重要なキーワードです。
「仕事を通しての幸せ」
また、多くの人が組織で働く時代になった現代では、人の幸せは組織のマネジメントによって決まるのです。
つまり、組織の重要な目的がそこで働く人を、仕事を通して幸せにすることだとドラッカーは言います。
それは報酬とかによるものではなく、仕事自体にやりがいを感じさせるような状態を作ることです。
「3つの役割(Tasks) 」
社会への「貢献」と「成果」、そして「人間の幸せ」というキーワードをもとに、社会の中に存在する組織が何をすべきかを考えれば、自ずと結論は見えてきます。
ドラッカーは、組織を運営するマネジメント層が組織を機能させ、貢献へと導くには次の3つの役割(tasks)を果たさなくてはならないと言います。
1.自らの組織に特有の目的と使命を果たす
(the specific purpose and mission of the institution)
2.仕事を生産的なものにし、働く人たちに成果をあげさせる
(making work productive and the worker achieving)
3.自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う
(managing social impact and social responsibilities)
以上の3つの役割の中で、1番目の「自らの組織に特有の目的と使命を果たす」については、あまり違和感はないと思います。
世の中には、自動車を作っている会社、ラーメンを提供している会社など様々な組織がありますが、それぞれの組織にはそれぞれに特有の目的と使命があり、それら固有の目的と使命を果たすことによって社会が成り立っています。
2番目の「仕事を生産的なものにし、働く人たちに成果をあげさせる」が、仕事を通して人間を幸せにするための項目で、人間は安定や高い給料を与えられることで幸せになるわけではなく、意味のない作業を続けても幸せにはなりません。
意味のある生産的な仕事に従事し、自らの責任を果たし成果をあげ、そのことで組織や社会に貢献することによって人間は自分の存在意義を感じるのです。
3番目の「自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う」については少し説明が必要で、組織が活動すれば社会に影響を与え、工場は公害を発生させるかもしれませんし、美味しいラーメン屋さんは熱や匂いを発散させているかもしれません。
組織は自らの目的や使命を果たすだけでなく、組織活動によって社会に与える影響も処理しなければなりません。
「知りながら害をなすな」
これは東京電力福島第一原発の例を挙げればよくわかると思いますが、東京電力は「関東地方に電力を供給する」という自らの目的と使命をしっかり果たしていたと思います。
しかし、あの事故は社会に大きな影響を与え、東京電力自身も大きな影響を受けました。
ただ、この社会的に責任について何かを約束するということは難しいことです。この点についてドラッカーは、プロとして「知りながら害をなさない」という約束だけはしなければならないと言います。
その最低限の約束がなければ人が人を信頼できない社会になってしまいます。
考えてみれば当たり前のことかもしれませんが、この人間として当たり前のことを改めて教えてくれるのがドラッカーなのです。
次は、国永先生の ドラッカー名言録12「企業が、より大きくなる必要はないが、不断に、よりよくならねばならない」を引用します。
ドラッカーは企業の規模についての良し悪しを論じたりはしないのです
要は、量やサイズではなくて、その質であり内容だと、かねてから主張していて、その代表著書である『マネジメント』の中のこの一節も、そうした考え方を端的に表したものにほかならないのです。
ドラッカーはコンサルタントとしては、大企業を対象とすることが多かったのですが、中小企業や中小の非営利法人についても、かねてから相談にのってきたし、いまでも取り扱っているのです。
この“至言”に関して思い出されるのは、かつて、「大きくなることも決して悪くない。しかし、その大きくなるなり方が問題なのだ。悪性腫瘍のようにメッタヤタラに大きくなるのではダメだ・・・・・・・」と語ってくれた言葉である。
また、最近の底の浅いベンチャーブームに対しても、企業家精神が旺盛なのはよいのだが、自分の「ワーク・オブ・ビジネス(Work of Business)=WOB」がどういうビジョンにより、どういう社会的貢献をしようとするの・・・・・などを十分に考えずに事業を立ち上げるのには反対である・・・・・といった趣旨の発言をしていたのも思い出す。
ここでいう「ワーク・オブ・ビジネス」という言葉は、かつてよくつかっていたが、いまは単に「ビジネス」とだけ称することが多く、その中身は「事業の本質」ということである。
したがって、ドラッカーにとっては事業の本質とその質が重要なのであって、サイズではないことがここからも読み取れる。
しかも、単に額に汗して頑張るというだけではいけないのであり、「努力は賞賛の対象にはなるが、事業活動は、規模の如何と関係なく、そこから生まれる成果、すなわち事業への社会の拍手喝采の度合いが問題なのである」という指摘も、ともに記憶しておきたい言葉である。
さらに同じ発想で「企業が生み出すのは、物でも観念でもなく、人間が値打ちありと認めるものである。いかに見事に設計された大きな機械でも、顧客に役に立たねば金属のスクラップにすぎない」とも発言している。
そして、企業はいつでも一種の冒険なのであって、それは、将来の、しかも極めて不確実な成果をあげるために現在の資源を投入することなのである。
したがって、こうした“賭け”としての企業は、闇の中への跳躍であるので、勇気と信念を必要とする行為なのである。
事業に関する決断は組織のサイズに関係なく、人を過去に拘束せず、未来の形成に一歩踏み込ませるものなのであるというのが、ドラッカーの事業の本質感なのである。
以上の様に、ドラッカーは組織(事業)の本質を非常に厳しく見ており、組織(事業)は世の中に貢献しなければいけないこと、そこで働いている人たちを幸せにすること、お客様に貢献することを厳しく戒めています。
そして、これは言い換えれば、経営理念に盛り込むべき内容と重なるのです。
一般的な企業の経営理念に盛り込むべき内容は以下の通りです。
1.お客さまに対する責任(貢献)、エクスターナル・マーケテイングで、要するに使命にあたり、お客さまへの貢献です。
2.従業員に対する責任(成果、幸福)、インターナル・マーケテイングで、従業員のレベルを上げ続け、成果を上げ、従業員の幸福に貢献するのです。
3.社会に対する責任(貢献)
4.株主に対する責任(成果)
永く成功する事業を作る上で、貢献、成果、幸せは欠かせないのです。
本日は、日本を代表するバリトン歌手で、東京芸術大学の名誉教授の多田羅迪夫先生(左から2人目)が本社を尋ねてくれました。
素晴らしい紳士でした。
今日も最高のパワーで、スーパー・ポジテイブなロッキーです。


_上半身のみ_resize-300x283.png)