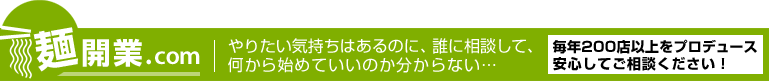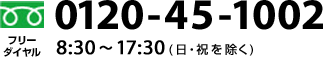本日のドラッカー・マネッジメントのテーマは、私自身にかかわることであり、自分自身のこととして、重く受け止め、これからの身の処し方のたいへん参考になりました。
起業家の身の処し方として、もう一つに面白い参考事例として、今月号、2015年6月号の「COURRIER JAPON」では、特集で「ジョブズは本当に「独裁者」だったのか?」を取り上げています。
ジョブズが亡くなったのは、2011年10月5日で、既に4年が経とうしていて、亡くなった当時は、多くの特集が組まれ、話題になり、ジョブズ亡き後のアップルの行方について、あまり好意的な見通しはなかったのです。
ジョブズ亡きアップルは、業績を大きく落とすと、予想をするアナリストが多かったのですが、ジョブズ亡きあともアップルはCEOテイム・クック等の経営により、世界最高の株式価値を更新し続け、ドル箱のiphoneは、サムスンのギャラクシーに大きく水を開け、中国等の新興国でも大きく成功しているのです。
このことは、ステイーブ・ジョブのようなカリスマ的リーダーである、独裁者亡きあとも、トップ・マネッジメント・チームが形成され、上手く機能していることを示しているのです。
そして亡くなる前のジョブズが望んだのは、自分のようなカリスマ的な指導者がいなくなっても、互いに協力し合って働く「社風」が存続していくことであったのです。
アップルを創業して、大成功させたころの早熟で、未熟で、暴君と呼ばれていた頃のステイーブ・ジョブズとアップルを一度追放された後、苦境のアップルを救うために古巣に戻った後のジョブズは、大きく変貌を遂げていて、ジョブズくらい、大きく自己変革出来た人間は数少なく、大きく変革出来たから、偉大な企業を創ることが出来、次に世代に引き継ぐことが出来たのです。
本特集では、初期のころのステイーブ・ジョブズと接したことのある人物、復帰後の大きく変革した後のジョブズと接していた人物に分けてインタビューしているのですが、誰もが指摘しているのが、ジョブズの常に進化している姿だったのです。
要するに、ジョブズ自身が過去の自分と決別し、常に変化するために、大きなエネルギーを使っていたのです。
本書では、・・・ジョブズと25年の付き合いがあったキャトルムは語る。「私にとってステイーブ・ジョブズは絶えず自分を変えていこうとする人でした。でも、そのことをほかの人に伝えようとしたり、話し合おうとしたりはしませんでした。だから彼が内省的な人間だったことが分かりにくいのかもしれません。」
・・・ジョブズは、学ぶことに貪欲だった。若き日のインド巡礼も学びの旅だったが、その後もネクストやピクサー、アップルで一緒に働いた人やメンターたちを見て、何か学べることがあれば、直ぐに吸収していったという。・・・
・・・アップルを追放された後、メンバーが協力し合うピクサーの社風に接したことだった。ピクサーのその社風を築いたのが、前出のエド・キャトルムだ。
キャトルムはピクサーをシッカリ掌握出来ていたので、ジョブズは製作に必要以上に介入させなかった。ピクサーの脚本家やアニメーターたちが、「ストーリーが平板」「キャラクターの個性が弱い」「デイズニーのアニメ部門のトップだったジェフリー・カッツエンバーグが口出ししてくる」といった問題に対処する様子を、ジョブズは距離を置いたところから眺めることが出来た。そして、「トイ・ストーリー」の成功後も、ピクサーのチームが同じような成功を何度も繰り返していく様子を見ていた。・・・
「ピクサーには、互いに協力し合うことで自分たちの仕事をよりよいものに変えていくコラボレーションの文化があります。ステイーブはそれに刺激を受けたと思いますよ」と「トイ・ストーリー」の監督、ジョン・ラセターは語る。
以下、たいへん興味深い記事が本書では続いており、いかに全員が協力し合うマネッジメント・チームの結成が大切であるか、協力し合う社内文化を作り上げることの大切さを明確に打ち出しているのです。
それが出来たために、ジョブズ亡きあとのアップルが大きな問題もなく、残された優秀なマネッジメント・チームで運営されているのです。
われわれは、日々、多くの書物、多くの出会い、多くの情報より、変革できるチャンス、自分にとって足りないものを教えられているのです。
ジョブズも常に、自分に足りないものを探し求めて、自己変革を遂げていたことがよく分かります。
ジョブズの人生こそ、破天荒な起業家から始まり、真の企業家に自己変革した偉大な事例であったのです。
本日も、ドラッカー選書「イノベーションと起業家精神(下)」(ダイアモンド社)に基づき、イノベーションについて、深くドラッカーから学んでいきます。
ぜひ、一緒にイノベーションと起業家精神を磨いていきます。
4創業者はいかに貢献できるか
◆創業者の問題
ベンチャー・ビジネスのマネジメントに関して重要なことを1つだけあげるとすると、チームとしてのトップ・マネジメント・チームの構築であるのですが、それは創業者自身にとっては、それは事の始まりにすぎないのです。
ベンチャー・ビジネスが発展し、成長するに伴い、創業者たる起業家の役割は変わらざるをえないのであり、これはたいへん難しいことではあるのですが、これを受け入れなければ、事業は窒息し、破壊されるのです。
もちろん創業者たる起業家は、これらのことについて「そのとおり」と同意するのは、事業の変化に対応せず、事業とともに自らをも挫折させてしまった他の創業者たちの悲惨な話を知っているのですが、何かをしなければならないことは知っていても、自らの役割をいかに変えたらよいかを知っている者は、ほとんどいないのです。
殆どの人は「何をしたいか」から考え、あるいはせいぜい「自分は何に向いているか」を考えるのですが、正しい問いは、下記の4つとその順序が大切なのです。
1.「客観的に見て、今後、事業にとって何が重要か」であり、急成長しつつあるベンチャー・ビジネスでは、創業者たる起業家は、この問いを、事業が大きく伸びたとき、さらには、製品、サービス、市場、あるいは必要とする人材が大きく変わったとき、必ず自問しなければならないのです。
2.「自分の強みは何か。事業にとって必要なことのうち自分が貢献できるもの、他に抜きんでて貢献できるものは何か」であり、この問いについて徹底的に考えたあと、はじめて次項目を質問するのです。
3.「本当は何を行いたいか。何に価値をおいているか。残りの人生とまではいかないまでも、今後、何をしたいか」
4.「それは事業にとって本当に必要か。基本的かつ不可欠な貢献か」を問うことができるのです。
第2次大戦後、大きな成功をおさめたニューヨークのペイス大学の例があり、エドワード・モートラ博士が1947年に創立したこの大学は、今日では水準の高い大学院をもつ学生数2万5000人というニューヨーク第3の大学にまで育っているのです。
彼のイノベーションは攻撃的なものだったのですが、彼は、1950年前後という、ペイス大学がまだ小さかった頃、すでに強力なトップ・マネジメントチームをつくりあげていて、そのメンバーは、それぞれが責任を負い、リーダーシップを発揮すべき担当分野をもっていて、彼自身は総長になり、そのうえ、助言と支援を得るために、独立した強力な評議員会を設置したのです。
◆千差万別
ベンチャー・ビジネスが必要とすることや、創業者たる起業家が強みとすること、あるいはその起業家がしたいと考えていることは、まさに千差万別であり、ポラロイドカメラの発明者エドウィン・ランドは、1950年代の初め頃まで、すなわち会社創立後の12年ないし15年間、自らマネジメントにあたっていたのですが、会社が急成長を始めた後は、トップ・マネジメントのチームをつくってマネジメントを任せたのです。
自分にはトップ・マネジメントの仕事は向いていないと判断したためであり、彼が貢献できるのは科学的なイノベーションだったので、彼は、自らを研究者と位置づけ、基礎研究担当の相談役になり、マネジメントはほかの者に任せたのです。
マクドナルドを構想し、創業したレイ・クロックも同じ結論に達し、彼は80歳すぎで他界するまで、社長をしていたのですが、日常の業務はトップ・マネジメントに任せ、彼自身は「マーケティングの良心」の役割を果たしたのです。
他界する直前まで、毎週自分の店を2、3軒訪れ、品質や清潔度や親しみやすさを点検し、顧客を観察し、話しかけ、耳を傾け、こうしてマクドナルドは、少なくとも彼が亡くなるまでは、ファーストフード業界トップを維持するうえで必要な変革を行いつづけることができたのです。
アメリカ太平洋岸北部のある建材商社では、若い創業者が、自分の役割はマネジメントではなく、小さな町や郊外にある、200か所の営業所の所長たちの面倒を見ることであると結論したのです。
事実上、事業を行っていたのは、彼ら営業所の所長で、彼らは、調達、品質管理、債権管理については、本社の支援を受けていたのですが、営業そのものは、本社の支援をほとんど受けずに、各地域においてセールスマン1人とトラックの運転手2人という陣容で彼ら白身が行っていたのです。
したがって、この建材商社の営業は、彼ら孤立した素朴な人たちの意欲、活力、能力、熱意にかかっていて、大卒は1人もおらず、高卒さえわずかで、この商社の創業者は、1月のうち12日から15日は、彼ら営業所長を訪ね、半日をともに過ごし、仕事や計画や目標について話し合うことを自分の仕事にしたのです。
この建材商社がほかの商社と違ったのはこれだけで、ほかはすべて同じだったのですが、創業者たるCEOの働きによって、同社は競争相手よりも3倍から4倍の速さで成長したのです。
今日、大手の半導体メーカーとして成功しているある会社は、3人の科学者によって設立され、この会社の場合、事業にとって必要なものは何かという問いに対する答えは3つあり、1つは経営戦略、1つは開発研究、もう1つは人材、とくに科学技術分野の人材育成で、3人は、それぞれについて誰が最も向いているかを明らかにし、それぞれの強みに応じて活動を分担したのです。
しかし実際には、人材育成を引き受けたのは、イノベーションに強い科学者で、その分野では学界の大物だったのですが、彼は、自分がマネジメントや人事にかかわる仕事に向いていると考え、ほかの2人もその考えに同意して、人材育成を担当することになったのです。
彼は「本当にやりたい仕事ではなかったのですが、それが私の最も貢献できることだった」と言っているのです。
◆手を引くこともある
創業者がいかに貢献できるかという問いが、創業者とそのベンチャー・ビジネスの双方にとって、つねに完全に満足のいく結果をもたらすとはかぎらなく、ときには、創業者が手を引くこともあるのです。
アメリカで最も成功している金融関連のベンチャー・ビジネスの1つにおいて、創業者の下した結論がこれで、彼は、トップ・マネジメントチームをつくり、会社が必要としているものは何かを自問し、自分自身と自分の強みについても考えた。そして、会社が必要とするものと、自分がしたいことの間にはもとより、自分の能力との間にさえ共通するものがないことを知り、やがて彼は、「1年半をかけて、後継者を育て、事業を引き継がせ、辞任したのです。」
彼はその後、金融以外の分野でベンチャー・ビジネスを3つ創業し、いずれも中堅企業に育て、そのいずれからも手を引いたのです。彼は新しい事業を育てることを好んだが、マネジメントは好まなかったのです。彼は、事業と別れることが、事業にとっても、自分にとっても幸せであるという事実を受け入れていたのです。
以上のように同じ状況にあっても、起業家によって達する結論は異なるのです。
ある有名な医療機関の創業者であり、その分野では主導的な地位にある人が、同じようなジレンマに直面し、それは、その医療機関がマネジメントと資金調達の両方ができる人を必要としていたのに対し、彼自身は研究者や臨床医であることを望んでいたことだったのです。
しかし彼は、自分が資金調達を得意とし、かつ大きな医療機関のCEOになる能力をもっていることを知っていて、「そこで私は、自分自身の希望を抑え、CEOとしての仕事と資金調達の仕事を引き受けることが、自分のつくったベンチャーと同僚に対する義務と考え、もちろん、自信がなかったり、理事会や相談相手が、君なら大丈夫と言ってくれなかったならば、そのような役は引き受けなかった」と、言っているのです。
本章を通して、私が一番肝心に考えていることは、起業家は変わり続けることが出来なければ、起業家で居続けることも、事業家で居続けることも出来ないということです。
もし、変わり続けることが嫌であれば、起業家にはなってはいけないのであり、早い段階で、誰かに譲るべきなのです。
そしていつかはこの世を去る時が来るのですから、いずれにしてもトップ・マネッジメント・チームは早い時期から作っておくことなのです。
画像は、シンガポールのマー・ライオンの近くのスペイン料理のレストランから、対岸にあるカジノ、マリーナ・ベイ・サンズを背景にしています。
料理と夜景の素晴らしいレストランでした。(4月26日の画像と同じ)
今日も最高のパワーで、スーパー・ポジテイブなロッキーです。


_上半身のみ_resize-300x283.png)