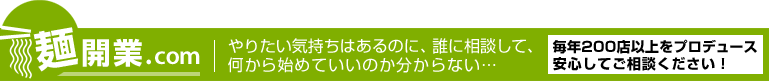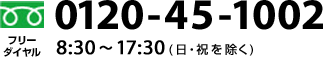本日のドラッカー・マネッジメントのテーマは、ビジネス・パートナーで、私は本田宗一郎に憧れて起業した、生粋のエンジニアであったので、本田宗一郎のパートナーである藤澤武夫に相当する、ビジネス・パートナーを創業間もないころから探し求めていました。
自分に不得手な分野は、マネッジメント、営業関係だと分かっていて、経理総務に明るい人とか、営業に明るい人とか、過去、いろんな人たちと一緒に仕事をしましたが、藤澤武夫の逸話を知っていたので、なかなか納得できる人とは巡り合うことが出来ませんでした。
既に、ビジネスを始めていたので、日々生きていくのに一生懸命で、ゆとりもなく、本田宗一郎のように、パートナーに恵まれるのを待ってから起業する訳にはいかなかったのです。
その頃の私は、マネッジメントのことも分からず、たくさんの失敗をしながら、例えれば、小舟が嵐の中を彷徨っているような状態であったと思います。
そのような状態をずっと続けている間も、ビジネス・パートナーのことは、頭の片隅から離れることはなかったのです。
今から20年前位に、総務に女性の責任者が入社し、更に十数年前から営業関係に女性たちが入社するようになり、当社は経営的に、安定するようになり始めたのです。
今になって振り返ると、それまでの男性の担当者と女性の担当者を比較すると、能力的な差は、多分なかったか、或いは、男性の方が能力は高かったと思いますが、能力の差より、もっと別の分野で大きな違いがあったのです。
私の過去の体験の中で、男性と女性を比較すると、一番大きな差はぶれない、一貫性があるかどうかであり、その差が、結果として仕事に成果に大きな差になって現われたのです。
当然、男性の中にもぶれない、一貫性のある人は多いと思いますが、おしなべて平均すると、女性の方がはるかに男性より、一貫性があったのです。
そして、私は過去を振り返ってみて、ビジネスの成果を出すのは、一貫性が欠かせないことに気付かされたのです。
現在も当社の役員の中で半数を女性が占めるのは、一貫性であり、私に対しても遠慮せずに、自分の意見を言える人たちであり、併せて、フレキシブルであり、女性特有のおもてなし、細やか、こだわりがあるのです。
会社を創業したころの私は、当然、ビジネス・パートナーとして、女性を考えたことはなかったのですが、今になっては、ビジネス・パートナーには女性が欠かせない存在であること、更に、上層幹部になればなるほど、一貫性、責任感、プロ意識が欠かせないことが分かってきたのです。
今期から、当社は給与システムを大幅に変える予定で取り組んでいて、今までは基本的に、年齢給と職能給が中心で、その上に、業績給があり、更にその上に、各種手当(役職、責任者等)が付与されていたのです。
これは、既に、20年前位に創り上げた当社独自の仕組みで、年功序列の場合は、年齢給だけですが、年齢給もある程度加味して、その上に、どれだけその仕事に精通しているかを表す職能給、更に、業績を上げたことによる業績給と分かれていたのです。
ところが、社員一人ひとりを経営者に仕立てるためには、この評価方法では足りないことが分かってきました。
抜け落ちていたのが、責任感、プロ意識、一貫性の評価項目であり、これからの時代は、これらが最も成果に大きな影響を及ぼすのです。
これらの項目は、一緒に仕事している上司であれば、部下を簡単に評価できる項目であるのです。
このような評価項目も、これから時代の変化とともに少しづつ変化していく可能性はありますが、責任感、プロ意識、一貫性については、永久に必要な評価項目ではないかと思います。
本日も、ドラッカー選書「イノベーションと起業家精神(下)」(ダイアモンド社)に基づき、イノベーションについて、深くドラッカーから学んでいきます。
ぜひ、一緒にイノベーションと起業家精神を磨いていきます。
◆パートナー
「自分は何か得意で何か不得意か」という問いこそ、ベンチャー・ビジネスが成功しそうになったとたんに、創業者たる起業家が直面し、徹底的に考えなければならない問題であるのですが、実は、そのはるか前から考えておくべきことであり、あるいは、ベンチャー・ビジネスを始める前に、すでに考えておくべきかもしれないことであるのです。
これは、第2次大戦の敗戦後という暗澹たる日本において、本田宗一郎が本田技研工業という小さなベンチャー・ビジネスを始めるにあたって行ったことで、彼は、パートナーとしてマネジメント、財務、マーケティング、販売、人事を引き受けてくれる者が現れるまでは、事業を始めなかったのです。
彼自身は、エンジニアリングと製造以外は何もやらないことにしていて、この決心が、やがて本田技研を成功に導いたのです。
今から30~40年前の日本では、ホンダ技研工業は、燦然たる急成長の企業で、常にマネッジメントの話題になっていた会社であり、本田宗一郎と藤澤武夫は、優れた経営者と参謀であると、常に話題になっていました。
普段、参謀役であった藤澤武夫が表舞台に立つことはなく、本田宗一郎と比べると、その存在は余り知られていないのですが、本田宗一郎も素晴らしい経営者でしたが、藤澤武夫も負けないくらい、素晴らしい人物であったことが、下記のウイキペデイアによれば、読み取れるのです。
藤澤武夫は、本田宗一郎の名参謀と言われ、本田は藤沢に実印と会社経営の全権を委ね、自らは技術者に徹し、2人の出会いは、ホンダ技研創業の1年後の1949年(昭和24年)8月、通産省(当時)技官の竹島弘の引き合わせで、本田宗一郎と出会い、ホンダの常務に就任し、東京営業所の開設を皮切りに、ホンダの財務並びに販売を一手に取り仕切るようになり、1952年(昭和27年)には専務、1964年(昭和39年)には副社長に就任し、派閥解消のための役員大部屋制や役員の子弟を入社させないといったシステムや1954年(昭和29年)に発表された本田の「マン島TTレース出場宣言」は藤沢によるものとされているのです。
1973年(昭和48年)、社長の本田とともに副社長を退き取締役最高顧問となり、この引退は後継育成を見極めた藤沢が決断したもので、本田はその藤沢の決断を聞いた際に藤沢の意思をくみ取り、引退を決断したと言われているのです。
創業25周年を前にしての両者の現役引退は、当時最高の引退劇とも評され、1983年(昭和58年)には取締役からも退き、藤澤は、その後、東京六本木で骨董店「高会堂」を開き、趣味人として余生を過ごし、影に徹した事、また経営者でありながら風流人な一面を持つ点、その卓越した経営手腕によって経営者達のファンが多く、またMBAコース等での教材として度々取り上げられる人物であるのです。
日本では本田の影に隠れて、あまり広く知られていない藤沢ですが、稀代の名参謀と呼ばれ、ビジネススクールでは度々取り上げられているのですが、本人は「私は経営学など勉強した事がない、何冊か手にとって読んだことはあるが、結局、その逆をやれば良いんだと思った。」と語っていたのです。
「経営者とは、一歩先を照らし、二歩先を語り、三歩先を見つめるものだ。」との言葉も残していて、現役時代の藤沢は、本社とは別に、銀座の越後屋ビルの1室を借り、調度品にいたるまで全て黒で統一し、その部屋にこもって経営戦略を練ったと言い、また洒落者で知られ、着流し姿で出社することもしばしばあったというのです。
無類の舞台好きであり、歌舞伎はもとより、世界各国のオペラ座に着物姿で観劇し、また、常磐津が玄人並の腕前で「文王」の名も持っていて、隠居後の藤沢は「自分は引退した老骨」と語り、自分から社の経営に口を出す事はせず、政界財界人との交流もあまりなく、むしろ先代の中村勘三郎や作家の五木寛之、谷崎潤一郎などの文化芸術人との世間話を楽しむ風流人として過ごしたのです。
上記のように舞台や音楽鑑賞を趣味とした藤沢に対し、本田はゴルフなどの行動的な趣味を持っていた事から、不仲説が浮上したことがあったのですが、当人たちは、互いが当時住んでいた地名の「下落合」(本田)、「六本木」(藤沢)と呼びあうなど良好な関係で、「いつも手をつないで一緒にいるのを仲良しとは呼ばない、私達は離れていても、今この瞬間、相手が何を考え、どうするかが、手に取るように分かる。」とも語っているのです。
洒落た紳士的な雰囲気の一方で、仕事に対して厳しく部下の不手際を叱る際は容赦なく厳しい言葉を浴びせ、大きな目と半開きぎみの口から次々と大きな声で怒鳴る仕草から当時流行っていた怪獣映画になぞらえ「ゴジラ」とも陰で呼ばれていたのです。
「本田神話のシナリオを書いた男」「名参謀」などの異名を持ち、「経営はアートであり、演出の基本は意外性である」と語っていて、「ホンダの社長は、技術畑出身であるべき。」という言葉を残していて、この方針はホンダにおいて現在まで忠実に守られており、初代の本田から現職の伊東孝紳に至るまで、歴代の社長7名全員が技術畑出身であるのです。
ホンダ技研は何度も危険な目に遭いながらも、以下のフォードのように、大きく落ち込むことがなかったのは、本田宗一郎が当初から、素晴らしい番頭役を見つけ、信頼してきたことが大きな要因になっているはずです。
ここに、ヘンリー・フォードという、さらに昔の、さらに教えられる例があり、フォードは、1903年に事業を始めることを決心したとき、ちょうど45年後の本田と同じ決心をし、彼は、苦手なマネジメント、財務、マーケティング、販売、人事を引き受けてくれる適当なパートナーを見つけてから、ベンチャー・ビジネスを始め、フォードも、本田と同じように、自分がエンジニアリングと製造の人間であることを知っており、自らをこの2つの分野に限定したのです。
彼が見つけたジェイムズ・カズンズは、フォードに劣らず会社の成功に貢献し、後にデトロイト市長とミシガン州選出上院議員を務め、もし、カナダ生まれでなければ、大統領にさえなれたかもしれないのです。
たとえば、1914年頃に導入した有名な1日5ドルの日給制、あるいはその先駆的な流通とアフターサービスなど、ヘンリー・フォードが考えたとされていることの多くは、カズンズが考えたものであって、むしろヘンリーが反対したものだったのですが、その後、ヘンリーは、あまりに有能なカズンズを疎んじ、1917年ついに追い出してしまったのです。
そのきっかけが、脱T型フォードと後継車開発というカズンズの主張であり、フォードは、まさにカズンズの辞任まで成長と繁栄を続けていたのです。
カズンズの辞任の数か月後、かつては、自分が何に向いていないかを知っていたヘンリー・フォードが、トップ・マネジメントの機能をことごとく手中にしたとき、長い衰退の時代に入り、彼は、その後10年間にわたって文字どおりまったく売れなくなるまで、T型モデルにしがみつき、フォードの衰退はカズンズの辞任の30年後、恐ろしく若いヘンリー・フォード2世が事実上倒産した事業を引き継ぐまで続いたのです。
5第三者の助言
前記の例は、ベンチャー・ビジネスの創業者には、外部の独立した人たちからの客観的な助言が必要であることを教えていて、成長しつつあるベンチャー・ビジネスは取締役会を必要としないかもしれないのです。
そもそも取締役会なるものの多くは、創業者が必要とする相談相手にはならないのですが、創業者は、基本的な意思決定について話し合い、耳を傾けるべき相談相手を必要とし、そのような人間は、社内ではめったに見つからないのです。
一番理想は、社内に第三者の意見の言える助言者を持つことであり、当社はこれを実現出来ている、数少ない中小企業であると言え、更に重要なことは、トップが耳に痛い話を聞く耳を持っていることだと思います。
◆最大の要件
創業者の判断やその強みを問題にできる人物が必要であり、第3者の立場にいる者が、創業者たる起業家に対し、質問をし、その意思決定を評価し、そして何よりも、市場志向、財務見通し、トップ・マネジメント・チームの構築など、ベンチャー・ビジネスが生き残るための条件を満たすよう、絶えず迫っていく必要があり、これこそ、ベンチャー・ビジネスにおいて起業家的マネジメントを実現するための最大の要件であるのです。
このように起業家としてマネジメントし、その実行をはかるベンチャー・ビジネスが、やがて大企業として繁栄するのですが、あまりに多くのベンチャー・ビジネス、とくにハイテクのベンチャー・ビジネスが、本章で述べてきた原理をしりぞけ、「それらは経営管理者のすることであって、われわれは起業家である」と、馬鹿にしているのです。
しかしそのような考えは、自由を意味しないで、無責任を意味し、態度と本質を混同していて、規律のないところに自由はなく、規律のない自由は放縦であって、やがて無秩序へと堕落するか、あるいは、時をおくことなく、独裁へと堕落するのです。
ベンチャー・ビジネスが見通しと規律を必要とするのは、起業家精神を維持強化するためであり、成功がもたらす要求に応えるためであるのです。
何よりも、ベンチャー・ビジネスは責任を必要とし、まさに起業家がこの責任を果たせるようにすることが、起業家的マネジメントであるのです。
財務、人事、マーケティングなど、ベンチャー・ビジネスのマネジメントについて述べるべきことはまだ多いのですが、それら具体的な問題については、すでに多くの書物が論じているのです。(巻末「参考文献」参照)。
本章では、企業であれ、社会的機関であれ、ハイテク、ローテク、ノーテクのいずれであれ、さらには1人の人間あるいは何人かのグループによるものであれ、また、中小企業のままでいようとするものであれ、第2のIBMたらんとするものであれ、ベンチャー・ビジネスなるものが、生き残り、成功していくうえで、決定的に重要な意味をもつ、いくつかのかなり基本的な原理を明らかにしたつもりであるのです。
画像は、シンガポールの有名な朝食の店に、ジェイソンが連れて行ってくれた時の画像です。
軽いお粥だと思って行ったのですが、ヘビーな朝食に驚きました。
シンガポール人のバイタリテイの素かも知れません。
今日も最高のパワーで、スーパー・ポジテイブなロッキーです。


_上半身のみ_resize-300x283.png)